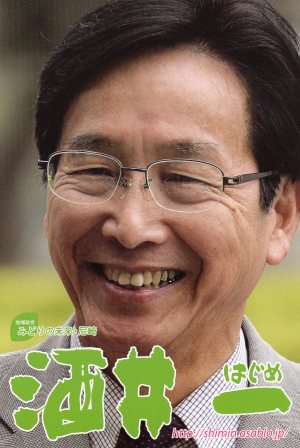ウクライナ戦争について 再び ― 2022/05/24
2022年5月24日
酒井 一
ロシアの侵攻を受けているウクライナを引き合いに出して、日本の防衛力の強化を主張する人たちがいます。
その主張は、「核共有」という名の核武装、「敵基地攻撃能力」という名の先制攻撃、などです。それは、中国や「北朝鮮」やロシアなどを「仮想敵国」とする論理の中での軍事のことで、これまで憲法9条をめぐって展開されてきた自衛権―専守防衛の枠組みを超えています。そして、この「軍事的論理」こそ、今のロシアが陥っている陥穽なのです。
第一の落とし穴を「地政学的論理」と仮に呼びます。軍事的関係と地理的関係を―なんといえばいいのか―強引に結びつける考え方です。
典型的には、仮想敵国を作り、それとの間に「緩衝地帯」を求めます。仲がよかろうが悪かろうが、隣国同士は折り合いをつけて暮らすしかないのに、「気に入らないからやっつけろ」というのです。ある国を、戦争もしていないのに敵国とする考え方もいかがなものかと思いますが、その国との間に「緩衝地帯」を求めるに至っては、「その『緩衝地帯』にも人々が住んでおり、国家や社会があるのですよ。緩衝地帯とはなんという失礼な・・・」と言いたくなります。
これは、まさに今のロシアが主張している考えです。曰く「NATOが東に拡大してロシアの国境に迫っている。これは許せない軍事的脅威だ。」「隣国ウクライナが非友好的になることは我慢できない」・・・近隣関係を軍事的関係に従属させ、軍事的関係で処理しようとする考え方です。
日本もかつてこの論理にはまって国を誤ったことがあるのです。
かつて日本は「朝鮮がロシアの勢力下にはいることは国家の危機だ」との理屈で日露戦争を起こし、朝鮮半島を植民地にしました。また「中国東北部(満州)はソ連に対する緩衝地帯」との考えのもと戦争を起こして傀儡「満州国」を立ち上げました。その次は、「中国が日本に敵対している」ということで攻め込んでいきました。
その際は「中国と日本は『同文同種』」と言って兄弟であるかのように言い、「暴支膺懲(暴虐な支那を懲らしめる)」という、とても上から目線なスローガンを掲げました。
「ウクライナとロシアは同じ民族」「ウクライナがナチズムになるのを阻止する」という今のロシアの「大義名分」とそっくりです。
そして、欧米側の支援のもと予想を超える中国の抵抗に戦争が長引き、兵力の逐次投入や補給兵站の不足という拙劣な戦争指導で苦戦したこと、さらに、戦えば戦うほど国際社会で敵が増え、世界の世論を敵に回して孤立していっていることも、似ている点が多いことに戦慄さえ覚えます。
私たちが、ロシアのウクライナ侵攻から教訓にしなくてはいけないことは、「軍事力の強化」云々ではなく、これからはこの「地政学的論理」の落とし穴にはまらないようにしなくてはいけない、ということ以外ではありません。日本の政権もマスコミも、ロシアのウクライナ「侵略」とは決して言わないのはなぜでしょうか。諸外国はすっきりと「侵略」と言っているにもかかわらず、です。そこに、かつての誤った戦争政策を真正面から反省していないこの国の病弊を見るのは無理筋でしょうか。
教訓にすべきことの第二は、これも適切な言葉が見当たらないのですが、「拡張された国益―民族主義的、イデオロギー的国益」とでも言うべき観念にとらわれてはいけないということです。
ロシアの行動の背景にはユーラシア大陸の大半に版図を拡げた旧ソ連時代の記憶があると思われます。そのもとではウクライナもベラルーシも、ジョージアも、ロシアを盟主とするソビエト連邦の傘下にあったのです。プーチンの振る舞いがその記憶にとらわれたものであるということは、争えないところでしょう。観念的に拡張された「民族主義的国益」です。
今、日本の軍備拡張を主張している人々の脳裏をよぎっているであろう「国益」の重要部分は三つの領土問題でしょう。尖閣列島(魚釣島)を中国と、竹島(独島)を韓国と、そして千島列島をロシアと、この三件の争いがナショナリズムを煽り、「国防」を主張する材料になっています。その先兵である「維新の党」の若い議員が言ったように、かれらの思想では「領土問題は戦争でしか解決しない」のです。
しかし、冷静に考えると、これらのいずれの争いも、「国の命運をかけて軍事的手段に訴えてでも」争わなくてはいけない「国益」がかかっているのでしょうか?私にはいずれの争いも経済的、社会的な打開の道がありそうに思えます。海底資源と漁業資源の話は経済的交渉のテーマになるはずです。海域の自由交通権問題も同じです。そこにお互いが軍事の論理とイデオロギーに絡みつかれた「国益」を持ち込みさえしなければ・・・。
イデオロギーと軍事的論理で化け物のように拡大された「国益」。その「国益」をその国の人々が暮らしていく上での利益にまで還元してしまえば、事態はもっと平明なものになるはずです。
今の世界で、国際紛争を引き起こし、多くをこじらせている大きな原因の一つがこの「拡張された『国益』=ナショナリズム」だと思います。
これから免れた国際紛争の解決の道筋を探らねばなりません。
以前にも書きましたが、まる一世紀歴史を巻き戻したかのようなロシアの侵略、そしてそれをめぐる軍事的地政学的論理とイデオロギー的ナショナリズムに絡みつかれた戦争拡大の危機¬―戦争を解決するに戦争をもってする―。今回も我々はそのディレンマから解き放たれないかに見えます
この危機に対抗するものは、今回大きく登場した、全世界の人々の「世界世論」とでもいうべき発言と発信の高まり以外にありません。国々が語る「国際世論」ではなく人々が発する「世界世論」です。この「世界世論」は情報・通信の飛躍的発達で、以前では考えられなかった規模と速度で影響を拡げます。
そしてその「世界世論」は、パリ不戦条約以来、現在の国連憲章、日本国憲法などに続く、戦争否定の思想に依拠しています。
「人間の尊厳」を基本として戦争を否定する考え方は、今や単なる「理想」「たてまえ」の域を超えて、国際法規の地位を確立し、世界の人々の「世界世論」をその基礎に持つようになったのです。
閑話休題
もう一つ、その陰に起きている恐るべきこととして、マスコミの視点の変化を挙げておかねばなりません。
ゴールデンタイムのテレビニュースに軍人が、解説者として、したり顔に出演し、戦争を地政学的に説明することが蔓延しているのです。地政学的には戦争は必然として説明されます。地政学的には「敵」を作った限りは緩衝地帯が必要となり、「国益」を拡張すれば、無際限な領土拡大が必要となるのです。ヒトラーの最も説得力のあったスローガンは「東に生存権を拡張する」だったのです。
もっと矮小なことですが、悲しむべき事に、情勢を狭い「軍事」で説明することが流行しだしました。それも軍人が出演して、です。
どう前線が動いたか、ならまだしも、アメリカが供与した「(おそらく155mm)りゅう弾砲」の数が戦局を左右するものであるといわれます。対戦車ミサイル「ジャベリン」や対空ミサイル「スティンガー」の効果が重大事として報道されるニュースに浸かってしまった我々に、戦争をやめさせたり、回避する道筋を考えたりすることは容易ではなくなってしまいます。
マスコミもかつてハマった落とし穴に気を付けてほしいものです。
酒井 一
ロシアの侵攻を受けているウクライナを引き合いに出して、日本の防衛力の強化を主張する人たちがいます。
その主張は、「核共有」という名の核武装、「敵基地攻撃能力」という名の先制攻撃、などです。それは、中国や「北朝鮮」やロシアなどを「仮想敵国」とする論理の中での軍事のことで、これまで憲法9条をめぐって展開されてきた自衛権―専守防衛の枠組みを超えています。そして、この「軍事的論理」こそ、今のロシアが陥っている陥穽なのです。
第一の落とし穴を「地政学的論理」と仮に呼びます。軍事的関係と地理的関係を―なんといえばいいのか―強引に結びつける考え方です。
典型的には、仮想敵国を作り、それとの間に「緩衝地帯」を求めます。仲がよかろうが悪かろうが、隣国同士は折り合いをつけて暮らすしかないのに、「気に入らないからやっつけろ」というのです。ある国を、戦争もしていないのに敵国とする考え方もいかがなものかと思いますが、その国との間に「緩衝地帯」を求めるに至っては、「その『緩衝地帯』にも人々が住んでおり、国家や社会があるのですよ。緩衝地帯とはなんという失礼な・・・」と言いたくなります。
これは、まさに今のロシアが主張している考えです。曰く「NATOが東に拡大してロシアの国境に迫っている。これは許せない軍事的脅威だ。」「隣国ウクライナが非友好的になることは我慢できない」・・・近隣関係を軍事的関係に従属させ、軍事的関係で処理しようとする考え方です。
日本もかつてこの論理にはまって国を誤ったことがあるのです。
かつて日本は「朝鮮がロシアの勢力下にはいることは国家の危機だ」との理屈で日露戦争を起こし、朝鮮半島を植民地にしました。また「中国東北部(満州)はソ連に対する緩衝地帯」との考えのもと戦争を起こして傀儡「満州国」を立ち上げました。その次は、「中国が日本に敵対している」ということで攻め込んでいきました。
その際は「中国と日本は『同文同種』」と言って兄弟であるかのように言い、「暴支膺懲(暴虐な支那を懲らしめる)」という、とても上から目線なスローガンを掲げました。
「ウクライナとロシアは同じ民族」「ウクライナがナチズムになるのを阻止する」という今のロシアの「大義名分」とそっくりです。
そして、欧米側の支援のもと予想を超える中国の抵抗に戦争が長引き、兵力の逐次投入や補給兵站の不足という拙劣な戦争指導で苦戦したこと、さらに、戦えば戦うほど国際社会で敵が増え、世界の世論を敵に回して孤立していっていることも、似ている点が多いことに戦慄さえ覚えます。
私たちが、ロシアのウクライナ侵攻から教訓にしなくてはいけないことは、「軍事力の強化」云々ではなく、これからはこの「地政学的論理」の落とし穴にはまらないようにしなくてはいけない、ということ以外ではありません。日本の政権もマスコミも、ロシアのウクライナ「侵略」とは決して言わないのはなぜでしょうか。諸外国はすっきりと「侵略」と言っているにもかかわらず、です。そこに、かつての誤った戦争政策を真正面から反省していないこの国の病弊を見るのは無理筋でしょうか。
教訓にすべきことの第二は、これも適切な言葉が見当たらないのですが、「拡張された国益―民族主義的、イデオロギー的国益」とでも言うべき観念にとらわれてはいけないということです。
ロシアの行動の背景にはユーラシア大陸の大半に版図を拡げた旧ソ連時代の記憶があると思われます。そのもとではウクライナもベラルーシも、ジョージアも、ロシアを盟主とするソビエト連邦の傘下にあったのです。プーチンの振る舞いがその記憶にとらわれたものであるということは、争えないところでしょう。観念的に拡張された「民族主義的国益」です。
今、日本の軍備拡張を主張している人々の脳裏をよぎっているであろう「国益」の重要部分は三つの領土問題でしょう。尖閣列島(魚釣島)を中国と、竹島(独島)を韓国と、そして千島列島をロシアと、この三件の争いがナショナリズムを煽り、「国防」を主張する材料になっています。その先兵である「維新の党」の若い議員が言ったように、かれらの思想では「領土問題は戦争でしか解決しない」のです。
しかし、冷静に考えると、これらのいずれの争いも、「国の命運をかけて軍事的手段に訴えてでも」争わなくてはいけない「国益」がかかっているのでしょうか?私にはいずれの争いも経済的、社会的な打開の道がありそうに思えます。海底資源と漁業資源の話は経済的交渉のテーマになるはずです。海域の自由交通権問題も同じです。そこにお互いが軍事の論理とイデオロギーに絡みつかれた「国益」を持ち込みさえしなければ・・・。
イデオロギーと軍事的論理で化け物のように拡大された「国益」。その「国益」をその国の人々が暮らしていく上での利益にまで還元してしまえば、事態はもっと平明なものになるはずです。
今の世界で、国際紛争を引き起こし、多くをこじらせている大きな原因の一つがこの「拡張された『国益』=ナショナリズム」だと思います。
これから免れた国際紛争の解決の道筋を探らねばなりません。
以前にも書きましたが、まる一世紀歴史を巻き戻したかのようなロシアの侵略、そしてそれをめぐる軍事的地政学的論理とイデオロギー的ナショナリズムに絡みつかれた戦争拡大の危機¬―戦争を解決するに戦争をもってする―。今回も我々はそのディレンマから解き放たれないかに見えます
この危機に対抗するものは、今回大きく登場した、全世界の人々の「世界世論」とでもいうべき発言と発信の高まり以外にありません。国々が語る「国際世論」ではなく人々が発する「世界世論」です。この「世界世論」は情報・通信の飛躍的発達で、以前では考えられなかった規模と速度で影響を拡げます。
そしてその「世界世論」は、パリ不戦条約以来、現在の国連憲章、日本国憲法などに続く、戦争否定の思想に依拠しています。
「人間の尊厳」を基本として戦争を否定する考え方は、今や単なる「理想」「たてまえ」の域を超えて、国際法規の地位を確立し、世界の人々の「世界世論」をその基礎に持つようになったのです。
閑話休題
もう一つ、その陰に起きている恐るべきこととして、マスコミの視点の変化を挙げておかねばなりません。
ゴールデンタイムのテレビニュースに軍人が、解説者として、したり顔に出演し、戦争を地政学的に説明することが蔓延しているのです。地政学的には戦争は必然として説明されます。地政学的には「敵」を作った限りは緩衝地帯が必要となり、「国益」を拡張すれば、無際限な領土拡大が必要となるのです。ヒトラーの最も説得力のあったスローガンは「東に生存権を拡張する」だったのです。
もっと矮小なことですが、悲しむべき事に、情勢を狭い「軍事」で説明することが流行しだしました。それも軍人が出演して、です。
どう前線が動いたか、ならまだしも、アメリカが供与した「(おそらく155mm)りゅう弾砲」の数が戦局を左右するものであるといわれます。対戦車ミサイル「ジャベリン」や対空ミサイル「スティンガー」の効果が重大事として報道されるニュースに浸かってしまった我々に、戦争をやめさせたり、回避する道筋を考えたりすることは容易ではなくなってしまいます。
マスコミもかつてハマった落とし穴に気を付けてほしいものです。